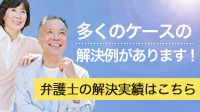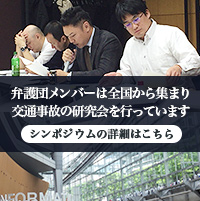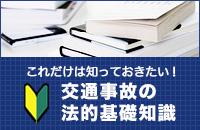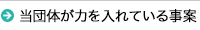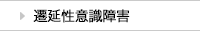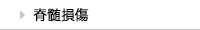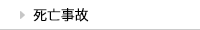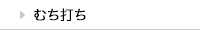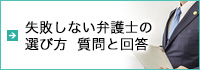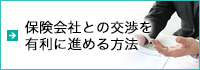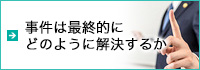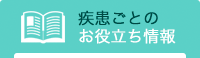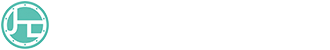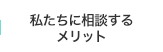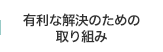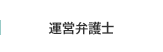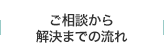脊髄損傷患者のソーシャルワーカーとの付き合い方
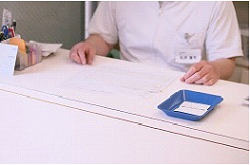
交通事故にあって、初めて病院に入院をしたと言う方も結構いて、「入院にはこんなものが必要なんだ」「20年前に母が入院した時はこうだったのにな。」と、病院のシステムの変りように驚かれる方もいます。
昔ならば病院の職員と言えば、医師・看護師・薬剤師・事務局員と言ったところでしたが、リハビリ専門の理学療法士やソーシャルワーカーを常駐させている病院もあります。
特に、ソーシャルワーカーは近年になって爆発的に普及したため、「理学療法士はまあわかるけど、ソーシャルワーカーってどういった仕事をしてるの?」と疑問に持たれる方も多いと思います。
しかし、ソーシャルワーカーはある意味、患者と一番密接な関係にあるため、理解してお付き合いすると、すごく心強い存在になります。
ソーシャルワーカーとは?
ソーシャルワーカーは、病院によっては「ケースワーカー」「医療社会福祉士」などと呼び方が違うことがありますが、基本的には「病院勤務の社会福祉士」と言うのが職務内容です。
厚生省が定める社会福祉士の業務方針は、
1.療養中の心理的・社会的問題の解決調整援助
2.退院援助
3.社会復帰援助
4.受診・受療援助
5.経済的問題の解決調整援助
6.地域活動
の6つにされています。
つまり、
「脊髄損傷で入院して会社を休んでいるけど、復職するにはどうしたらいいのかな?」
「退院後のリハビリはどこに通えばいいのだろう」
「交通事故で脊髄損傷になったのに、加害者から治療費が払われず、入院費の支払いができそうにない」
「退院しても、仕事をクビになったので収入がない」
「転院先が見つからず困っている」
「脊髄損傷なので身体障害者の申請をしたいけど、手続きはどうしたらいいの?」など、医療行為には直接関係しないものの、入院を起因とする問題の解決の手助けをしてくれます。
本来病院のソーシャルワーカーは社会福祉士の資格は必要ないのですが、必須としている医療施設が多く、中には看護師や保健師の資格を持ったソーシャルワーカーもいます。
そのため、ソーシャルワーカーは医療や社会保障、公的な支援や手続きに関して幅広く情報を持っているので、ソーシャルワーカーとうまく連携できるかが、患者にとっても重要となります。
特に、脊髄損傷の患者は経済的なことに加え、将来的な社会復帰や国に対する公的な手続きなど、悩み事が山積みとなっているため、ソーシャルワーカーが病院に在籍している場合にはすぐにでも相談をした方が良いです。
しかし、すべての病院にソーシャルワーカーがいるわけではなく、またいたとしても力量不足等から頼れないと言う事もあります。
そのような場合には、早期から保険会社との交渉と併せて弁護士に依頼をした方が、交通事故に精通した弁護士ならばアドバイスをしてもらえます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故による脊髄損傷で休業補償の請求では、入院期間や通院した日のほかに、医師が自宅療養の必要性を認めた場合には、通院をしなかった日に対しても休業補償を請求できる。
脊髄にかかる衝撃が保護している範囲の限界を超えると脊髄を構成する神経が傷ついて脊髄損傷になる。脊髄損傷となった場合には、まずは弁護士へ相談するのが望ましい。
交通事故による脊髄損傷で入院中の入院雑費は、日額1,100~1,500円で計算されるが、それを上回る請求をする場合には立証証拠を揃えて弁護士から請求してもらう方がよい。
脊髄損傷による損害賠償の内訳は、大きく分けて積極的損害と消極的損害の2種類があり、もともとの損害に対する補償の性質が異なる。
脊髄損傷で行われる手術は、神経除圧術と脊髄固定術があるが、どちらも脊髄損傷を根本から治癒するものではなく、対処療法としての手術になる。