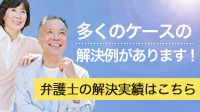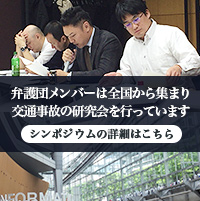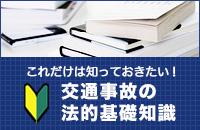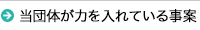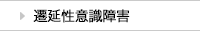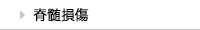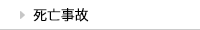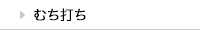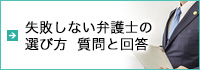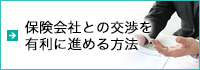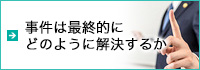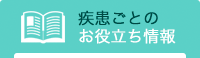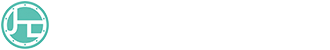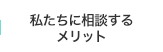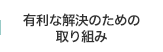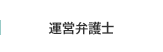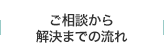死亡事故においての刑事罰、行政罰、民事責任について

交通事故、特に死亡事故など人身事故を起こした場合には、加害者には3つの責が課せられます。
1つ目は道路交通法違反の刑事罰、2つ目は自動車免許停止・取り消しなどの行政罰、3つ目が壊した物品や人身傷害・死亡事故に対する民事責任(損害賠償)です。
つまり、死亡事故を起こした加害者の多くは、警察に拘束された上で裁判となり、免許取り消しの通知が来て、被害者遺族から被害者死亡に対する損害賠償請求をされるというのが、同時に並行して行われることになります。
なかでも、刑事罰は死亡事故の場合には懲役刑もあり得るため、加害者・被害者遺族双方が大きな関心を持つ項目になります。
死亡事故の場合は、「自動車運転過失致死傷罪」(最高懲役7年)、飲酒・薬物使用などの正常ではない状態での運転による死亡事故であれば「危険運転致死傷罪」(最高懲役20年)に問われます。
ひき逃げなど、そのほかの罪状が複合すると、最高で30年という事もあります。
しかし、死亡事故の加害者が今まで道路交通法の違反がなく、死亡した側の過失が多くあるような場合は、罰金刑だけであったり、執行猶予つきの禁固刑で済んだりすることの方が多いです。
実際、死亡事故の加害者が交通刑務所や一般刑務所に懲役や禁固刑で収容されるのは、死亡事故全体の数パーセントしかありません。
重罰に科されるケースも
そのため、死亡事故の遺族が「死亡事故の加害者を刑務所に入れて欲しい」「加害者の懲役刑を長くしてほしい」と希望していても、実際に出される判決は被害者遺族の希望とは程遠いということがあります。
反対に、「元はと言えば、泥酔して大通りの車道に飛び出した父の方が悪いので、運転手の方を罪に問わないで欲しい」と遺族が嘆願しても、無罪にはなりません。
死亡事故の場合、刑事罰的には罰金刑・禁固刑・懲役刑の順で重くなっていきます。
死亡事故の中でも、死亡事故を起こす前は違反がなく、被害者遺族への賠償も済んでいる、もしくは自動車保険に加入しているなどして十分な補償が行える加害者の多くは、罰金刑や禁固刑の執行猶予付の判決がおりることがほとんどです。
つまり、被害者遺族側が加害者に対して抗議をしたい場合には、刑事裁判が終わるまでは示談をしない方が良いということになります。
逆に加害者側の立場からすれば、自動車保険に加入していて被害者遺族に対して十分な補償が行え、示談が済んでいるというのは刑事裁判でも有利になることとなります。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
死亡事故の加害者への損害賠償請求には、通夜~法要、埋葬までに要する葬儀関係費用を含められる。一般的な請求上限額は150万円であり、個々の要件により上限額は増減する可能性がある。
子どもの死亡事故の場合、成人の死亡事故に比べて過失割合が減算されたり、慰謝料が低めに設定されているため、注意が必要である。
死亡事故で逮捕されると、取り調べと送検を受けて最短で3日、最長で23日以内に不起訴か起訴かが決まる。起訴されれば裁判を経て量刑が決まる。
死亡事故の積極的損害と消極的損害は、受傷だけの交通事故の請求項目に加えて、葬儀代などの項目を追加して請求することができる。
高齢者の死亡事故の場合、被害者が年金生活か、給与所得者か、無年金者なのかで逸失利益の計算が大幅に変わってくる。