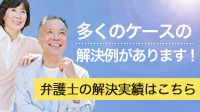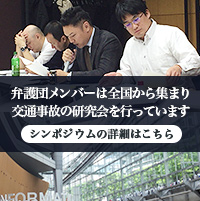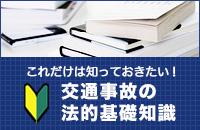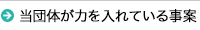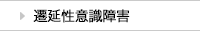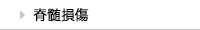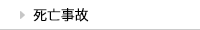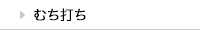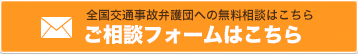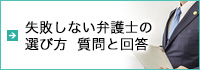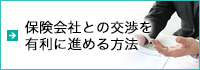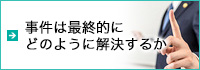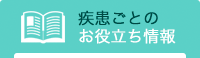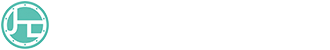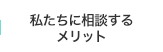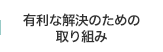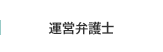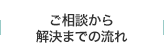交通事故の症状固定後に死亡した場合の逸失利益の支払いは?

【質問】
主人が交通事故に遭い、脊髄損傷の後遺症で後遺障害3級の認定を受けました。
症状固定・後遺障害認定が終わり、加害者側の保険会社と示談交渉をしようとした矢先に、主人が入院中の病院で心臓まひにより死亡しました。
病院のカルテからも治療に関して医療過誤の疑いはなく、交通事故の脊髄損傷に起因するものでもなく、急性の心臓麻痺ということでした。
しかし、示談前に夫が心臓麻痺で亡くなったことで、逸失利益に関してもめています。
「逸失利益は交通事故に遭わなかった場合、症状固定後に得られたであろう給料の補填をするもので、今回のように症状固定後3カ月で亡くなられている場合には、3カ月分しか支払わない」と言ってきました。
症状固定をし、後遺障害認定が終わった直後の説明では、逸失利益は平均余命から計算されるため、ご主人の年齢からすると28年の余命になります」と言われていただけに、あまりの違いに驚いています。
この場合、保険会社が言うとおり、症状固定から死亡までの3カ月分の逸失利益しか受け取ることができないのでしょうか?
【回答】
交通事故の症状固定から示談成立までの間に、交通事故の被害者が亡くなるのはあまりないことですが、実際に起こった場合には、症状固定から死亡までの分を逸失利益として認めるのか、それとも症状固定時の患者の平均余命から逸失利益を算出するのかで、かつて裁判で争われた事例があります。
この裁判は上告するたびに逆転判決が出るなど、裁判所の判断も難しいものであったと言えます。
最高裁の判決は、「交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予想されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定期間の認定上考慮すべきではないと解するのが相当である」としています。
かみ砕いて表現すると、「交通事故の時点で、余命2カ月のガンであるとかの特別なケース以外は、症状固定して逸失利益を考える際に死亡していても、普通に平均余命で計算しましょう」ということになります。
今回のケースでは、3カ月分の逸失利益だけにするというのは保険会社の暴論に近く、平均余命による逸失利益の計算が妥当と言えます。
それでもなお、保険会社が応じない場合には、弁護士を雇って対抗した方が良いでしょう。
逸失利益の差が年収によっては5000万円以上になる可能性もあるため、保険会社に負けない示談交渉をする必要があります。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故の怪我が原因で入院した場合、被害者は個室を希望される場合が多い。しかし過去の判例からすると、そのほとんどは個室料金の請求が認められていない。
死亡交通事故による保険金の相続も、相続人同士の同意があれば、話し合いで相続内容を決めることができる。
交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。
加害者の持病が原因で起こった交通事故の場合でも、加害者に責任能力を問うことができる可能性が非常に高く、損害賠償請求もできる可能性が高い。
交通事故に遭い受験ができなかった場合には、交通事故の被害者の学力によっては、1年分の年収に当たる損害賠償金を請求することができる。