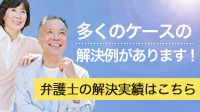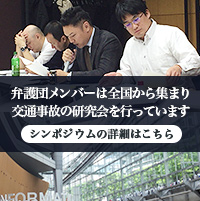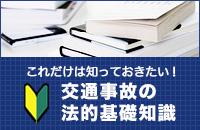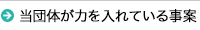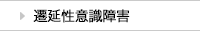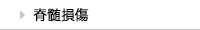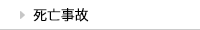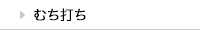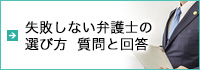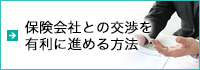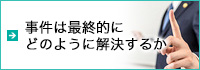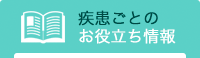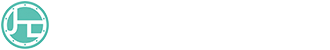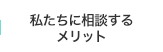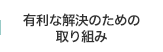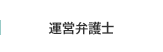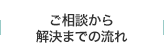脊髄損傷によって引き起こされる自律神経障害について

脊髄損傷のなかでも、より症状や後遺障害が重篤になるのが脳に近い頚髄の損傷であり、頚髄損傷に特有かつ発生しやすいのが「自律神経障害」です。
自律神経とは、意思とは関係ない生命維持のために働く神経のことであり、これが損傷することでしびれや麻痺以外にもさまざまな障害を引き起こします。
この自律神経障害のひとつが、「体温調節機能の低下」です。
Th6以上の脊髄損傷により、放熱、産熱のバランスをとることができなくなります。
外界の温度によって低体温や高体温になってしまうために、室温や衣類での調節が欠かせません。
また受傷後数時間~数日の間に40度以上の高体温となるケースがあり、脳幹による体温調節機能の低下、麻痺している場所の発汗機能低下が原因ではないかと考えられています。
Th5以上の脊髄損傷では、腹部の臓器、下肢の交感神経系への伝達が断たれるために、この領域にある「血管運動神経の障害」が発生します。
自律神経の機能として、重力により下肢に流れた血液は反射的に脳の方へ押し返されます。
この働きがなくなることで起立性低血圧を引き起こすようになるので、端座位(腰かけ座位)や起立位をとることでのリハビリを早い時期から始めることが予防になります。
激しい痛みや骨化が起こることも
知覚がないはずの部分から激痛やしびれを感じる「知覚脱失性疼痛(異常疼痛)」もまた、自律神経障害のひとつとされます。
軽症の場合は体を動かしたりさすることでよくなりますが、痛みが強いときには電気刺激療法や温熱療法、薬物療法や心理療法を行います。
原因がはっきりしないために改善が難しい症状です。
自律神経の障害に加え、浮腫によって不要なカルシウムなどが組織内に留まって、腱や靭帯、関節包などに異常な骨ができるのが「異所性骨化」です。
受傷後半年ほどのあいだに、股関節や膝・肩・肘・足などの関節周囲に発生する傾向があります。
骨が大きくなるとともに関節の周囲が腫れて、熱感、発赤などをともない、関節の可動域が制限されます。
これらの自律神経障害は、予防できるものもあれば、予防が難しく上手につきあっていかなくてはならないものもあります。
交通事故で脊髄損傷になってしまったときには、後々の損害賠償請求に対処するときのためにも、どこにどんな症状があるのか、「気のせいかも・・・」と思わずに医師にきちんと話し、しっかり診断してもらって、必要な補償に備えることが大切です。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故による脊髄損傷は、症状に応じて後遺障害等級が分かれる。慰謝料に大きく影響する部分であるため、具体的な症状と等級を照らし合わせ、把握するのが望ましい。
脊髄損傷の症状は四肢の麻痺が代表的なものであるが、一見して脊髄損傷によるものとは分からない症状もあるため注意が必要である。
脊髄損傷の症状は、交通事故発生からしばらくしてから現れることもある。事故現場で自覚症状がなくても、警察を呼んで交通事故の報告をしなくてはならない。
脊髄損傷は損傷の程度により、足先の痺れや、下半身麻痺であったりと症状にばらつきがある。交通事故による怪我が原因で生活が困難になった場合、リフォーム費用を加害者側に請求できる可能性がある。
交通事故で受傷した脊髄損傷は、後遺障害等級の認定を受けられれば高額の慰謝料を見込める。今後の人生を大きく変える怪我であるため、納得いく金額を受け取るために、弁護士に相談するべきである。