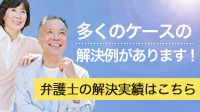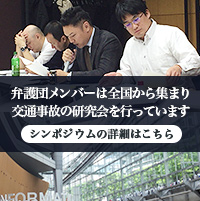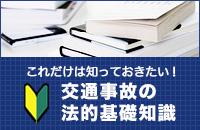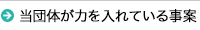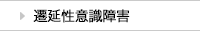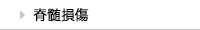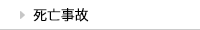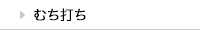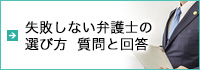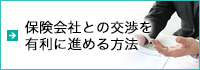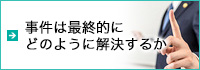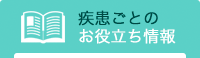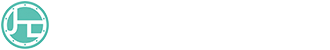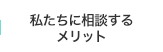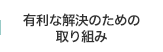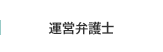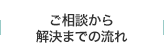死亡事故の過失割合でもめる理由はどんなものがある?
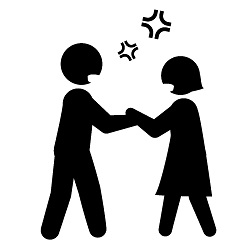
交通事故において双方の言い分が違うことはよくあり、一方が亡くなる死亡事故においては、生きている方の主張がまかり通ってしまい、死亡事故の被害者遺族との紛争の原因となります。
死亡事故でも歩行者と自動車の場合は、歩行者の優先の大前提から、「歩行者が酔って車道で寝ていた」「片側3車線の大通りで、信号付の横断歩道が付近にあるにもかかわらず、ガードレールを乗り越えて道路を横断した」といったような状況でもない限り、歩行者の過失が0かきわめて低いとの前提で警察も調査をします。
しかし、自動車対自動車の場合は、片方の過失割合が0となることは極めて稀で、双方が過失割合を負うことになります。
交通事故の過失割合は、今まで何千万件も交通事故があり、何万件もの判例があるため、過失割合の基準というものが存在しています。
そのため、交通事故が起こった際に保険会社が提示してくる過失割合は、その基準によるものが多いです。
なぜ過失割合でもめるの?
過失割合でもめる理由は、お互いの過失割合を足した時には10となることです。
過失が全くなければ0ですし、一方的な過失があれば10になります。
つまり双方の過失が0であったり、10であったりすることはありえないのです。
この過失割合は、保険金の支払いにおいて大きな問題となります。
過失が0ならば全面的な補償を保険会社から受けることができますが、過失が10であれば特約に加入していない限り保険金は支払われません。
つまり過失割合が6であれば、治療費などは40%しか支払われないため、少しでも保険金の支払いを増やそうと、過失割合の押し付け合いが起こるのです。
死亡事故の場合には、さらに状況は深刻になります。
死亡事故の被害者に対する損害賠償金は1千万単位になることもあり、過失割合が1変わるだけで数百万円の違いになるため、死亡事故を起こした側からすれば死活問題と言えます。
また、過失割合は刑事裁判の結果とリンクしていないとはいえ、影響があります。
死亡事故の状況が通常ならば4:6の過失割合になるのに、裁判の事故状況の分析からスピード違反や信号無視などが分かり、8:2に変化するといったこともあり得ます。
刑事裁判において、示談が済んでいるかどうかも大きなファクターになります。
死亡事故の遺族との示談が済んでいる場合には、裁判官もそれを情状酌量の判断材料とすることもあるので、示談を急ぐ加害者もいます。
そういった場合には、被害者が有利な過失割合で示談に応じる加害者もいるため、死亡事故の場合必ずしも過失割合でもめるとは限りません。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
死亡事故当時無職であった場合には、逸失利益を0円として保険会社は計算をしてくるが、裁判所の判断によっては逸失利益を認める判決が出ることがある。
ご家族が死亡事故に遭われると、正常な判断ができなくなる可能性があります。抜けのないよう、損害賠償を全て請求するためにも、その種類についてはしっかりと把握しておく事が大切です。
家族が死亡事故に遭った場合には示談交渉を行うが、損害賠償請求権の時効は事故日から5年である。しかし、提訴や催告、承認などで時効の更新(中断)を行う事が出来る。
家族が死亡事故に遭った場合、警察や保険会社、あるいは葬儀社とのやりとりをしなければならない。それらの負担を抑えられるメリットがあるため、弁護士へ依頼するのもひとつの手段である。
死亡事故で弁護士を雇う利点は、公的な手続きを代行してもらえる、加害者側の交渉を任せられるので直接会わずに済む、保険会社と交渉して保険金の増額が望めるなどがある。